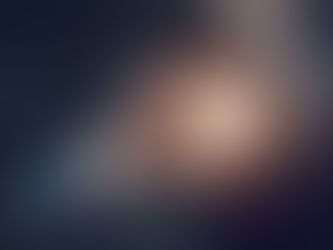営業のテクニックとは?営業で使える・役に立つテクニックを解説
- プロテア 株式会社
- 6 日前
- 読了時間: 13分
更新日:5 時間前
「提案しても決裁者の反応が薄い」「あと一歩でクロージングできない」など、成果が伸び悩むとき多くの営業担当者は“テクニック不足”を漠然と感じます。しかし、闇雲に話し方を変えるだけでは効果が続きません。
この記事では、商談前・商談中・クロージングの各フェーズで再現性高く使える営業テクニックを体系化し、具体例とともに解説します。
読み終えるころには、自分の強みを生かしながら成約率を高める方法が明確になり、明日からのアクションプランを自信を持って設計できるはずです。
営業テクニックの基礎理解
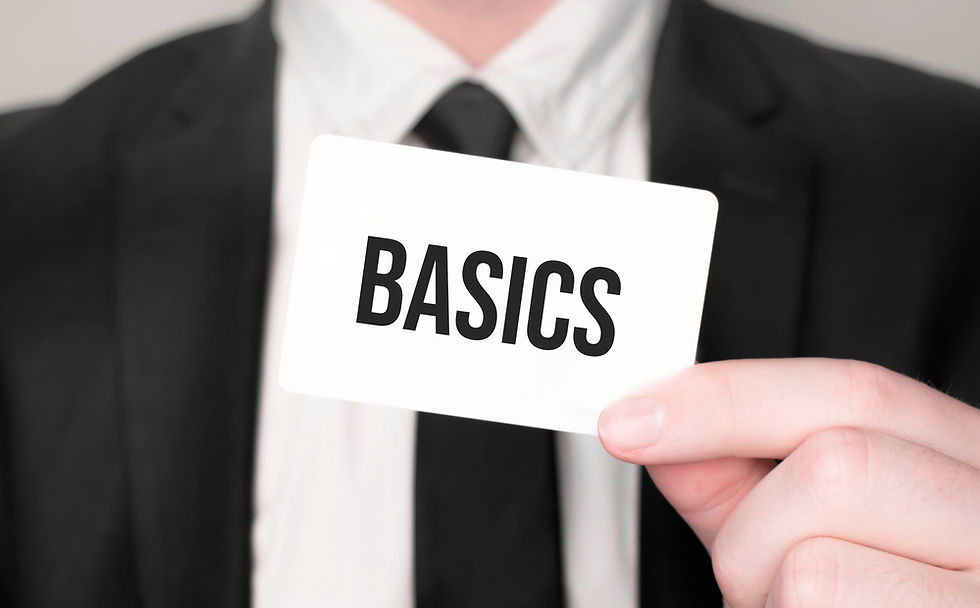
営業成果を高めるには、個々の営業スキルだけでなく「テクニックの役割」と「実行の倫理」を正しく把握することが欠かせません。
概念を把握すると、後段で紹介する実践的手法も一貫した意図をもって選択できます。
テクニックとスキルの違い
成果を左右する3要素
テクニック種類一覧
心構えとモラル
これら4つの観点を押さえることで、テクニックを状況依存の小技ではなく成約率を高める再現性ある仕組みとして活用できます。
それぞれ順番に解説していきます。
テクニックとスキルの違い
テクニックは「短期間で成果を伸ばす再現手順」、スキルは「長期的に高める総合能力」です。テクニックはパターン学習で速習できますが、スキルは経験と反復が不可欠です。混同すると問題点が見えにくくなるため、まず「型」と「力量」を分けて改善計画を立てることが重要です。
成果を左右する3要素
成果は「戦略」「対人スキル」「実行テクニック」の三位一体で決まります。戦略がズレていれば誰に何を提案しても成約は難しく、対人スキルが乏しければ信頼構築に時間がかかります。テクニックは残り二要素を補完する役目を担い、三つのバランスが揃って初めて最大効果を発揮します。
テクニック種類一覧
営業テクニックは「情報収集」「質問設計」「提案構成」「クロージング」「フォロー」の五分類で整理できます。分類しておくと自分の弱点が可視化され、研修や書籍を選ぶ際の指針になります。各分類に代表的なフレームワークや会話例を紐づけておくと、商談ごとに使い分けやすくなります。
心構えとモラル
テクニックを駆使する際は「顧客価値への貢献」を最上位に据える必要があります。数字達成だけを目的にすると、過度な圧迫や誇張表現に陥りやすく信用を損ねる原因となります。倫理観を保ちながらテクニックを使う姿勢が、長期的な顧客ロイヤルティとリピート受注につながるでしょう。
商談前に使う営業テクニック
商談準備は成約率の約8割を決めるとも言われます。
ここでは面談前に実施できる5つのテクニックを整理し、効率的に「勝てる設計図」を描く方法を示します。
ターゲットリサーチ術
ヒアリング設計のコツ
自分の強みの言語化
仮説ニーズの設計
キーパーソン攻略法
準備精度を高めると商談中の質問や提案が的確になり、自然に受注確度が上がります。
それぞれのテクニックについて順番に解説していきます。
ターゲットリサーチ術
企業サイトやIR資料、SNS投稿を多角的に調査し、業績トレンドや経営課題を仮説立てます。一次情報を重視すると、提案に「御社ならでは」の視点が盛り込めるため差別化が容易です。無料ツールでも十分に情報は得られますが、リサーチ時間を短縮するために検索クエリをテンプレ化しておくと効率的です。
ヒアリング設計のコツ
面談冒頭で聞く質問をシナリオ化し、目的・背景・指標の三段構造で整理します。質問数は多過ぎても少な過ぎても情報が欠落するため、想定回答を記入した台本を作ると過不足を防げます。また、各質問には「質問意図」を明記し、聞く順序を流れで覚えると対話が自然に進みます。
自分の強みの言語化
成果事例を「課題→施策→結果」の順で箇条書きにし、具体的数値を添えます。これをストックしておくと、顧客属性に合わせて短時間で事例を差し替えられます。数字の裏付けがある実績は説得力が高く、ヒアリングで得た課題と即座にひも付けられるため提案が刺さりやすくなります。
仮説ニーズの設計
リサーチ情報を基に「現状」「理想」「阻害要因」を一枚のシートへ整理します。阻害要因を複数列挙すると、質問の優先順位が明確になりヒアリング後の提案スピードが上がります。仮説が外れても気づきが得られるため、リスクではなく学習材料として位置付けると改善が早まります。
キーパーソン攻略法
決裁者と実務担当者では関心度合いが異なります。役職ごとに期待価値をマッピングし、決裁者にはROI、担当者には業務負荷軽減を訴求するなどメッセージを分けます。名刺情報やSNSで得た興味関心を活用し、商談前に共通の話題を準備すると初対面でも心理的距離を縮められます。
商談中に役立つ営業テクニック
面談が始まると準備通りに進まない場面も多くなります。リアルタイムで状況を読み取り、5つのテクニックを組み合わせることで会話を主導しながら顧客理解を深められます。
SPIN質問法で深掘り
PASONAで提案構成
ラポール構築の瞬発技
ストーリーテリング活用
沈黙と間の作り方
瞬時の判断が求められるフェーズでも「型」を持っていれば落ち着いて対応できます。
それぞれテクニックを順番に解説していきます。
SPIN質問法で深掘り
Situation・Problem・Implication・Need‐Payoffの順に質問を重ねることで、顧客が言語化していない本質的な課題に到達できます。重要なのはProblemとImplicationで時間をかけ、「放置すればどんな損失が起きるか」を顧客自身の言葉で語ってもらうことです。Need‐Payoffは提案前の期待値確認として機能します。
PASONAで提案構成
Problem→Affinity→Solution→Offer→Narrowing down→Actionの順に語ると、課題共有から行動喚起まで一気通貫で説明できます。Affinityでは「同じ課題を解決した事例」を例示し、共感を醸成します。Narrowing downでは限定条件を示し、行動に踏み切る理由を明確化することがポイントです。
ラポール構築の瞬発技
初対面で信頼を得るには、声のトーン合わせやミラーリングなど非言語コミュニケーションが効果的です。ただし過剰に模倣すると不自然になるため、相手の呼吸ペースを意識的に追従する程度が自然です。共通項の提示より「相手を理解しようとする姿勢」が信頼の土台になる点を忘れないようにします。
ストーリーテリングの活用
数値データだけでは行動意欲が高まりにくい場合、似た業界の成功談を物語として語ると「自分事化」を促せます。ストーリーは時系列とキャラクターを入れ、課題発生から変化後の未来像まで描写します。情緒的理解が進むと、導入コストより得られる価値に意識が向くため提案が受け入れやすくなります.
沈黙と間の作り方
成約に近づくと相手は情報を咀嚼するため、一時的に沈黙する場面が増えます。ここで急いで話し続けると思考を妨げるため、三秒ほど待つことで自然に相手が発言しやすくなります。適切な間を取ることで「押し売り感」が減り、顧客が自発的に意思決定へ踏み出す心理状態をつくれます。
クロージングの営業テクニック

クロージングは提案価値を確定させ、最終決断を後押しする工程です。
下記の5つのテクニックを組み合わせることで躊躇を解消し、WIN‐WINの着地を目指せます。
Yes誘導クロージング
限定性と希少性の活用
反論処理のフレーム
デシジョンツリー提示
条件交渉の切り札
決断を急かすのではなく、合理的に背中を押すことが継続的な関係強化につながります。
それぞれ順番に解説していきます。
Yes誘導クロージング
過去の質問で「はい」と答えた内容を三つ連続で確認し、心理的な同意の流れを作ります。その勢いで契約意思を確認すると抵抗感が低減します。質問は事実確認→期待効果→導入意欲の順に組むと自然です。乱用すると誘導感が強まるため、顧客の理解度を確かめながら使います。
限定性と希少性の活用
提供価格や納期の優遇を期間・数量で限定すると、意思決定の先延ばしを防げます。ただし虚偽の締切は信頼を損なうため、根拠ある条件に絞ります。メールでも同じ条件を明示し、口頭説明との一貫性を保つと誤解が減ります。
反論処理のフレーム
価格・導入工数・社内稟議など想定される反論を「同意→理由確認→提案」の三段構成で対応します。まず共感を示し、次に懸念の真因を質問で深掘りし、最後に具体的な解決策を提案します。フレームを覚えておくと想定外の質問でも冷静に対処できます。
デシジョンツリー提示
条件を枝分かれで示すと、複数の選択肢を視覚的に比較でき決裁がスムーズです。最終的に推奨案へ自然に収束する設計にすると、顧客は自分で選んだ感覚を持ちながら納得できます。図解には紙でもホワイトボードでも構いませんが、要素は3〜4つに絞ると理解しやすくなります。
条件交渉の切り札
価格以外の価値(導入サポート期間や追加機能)を交渉材料にすると、値引き一辺倒の議論を防げます。譲歩の順序を事前に決めておき、低コストで提供できるが顧客価値が高い項目から提示すると納得感が高まります。相互譲歩の姿勢を示すことで関係性も強固になります。
オンライン特有の営業テクニック
遠隔商談では対面とは異なる制約があり、映像・音声・チャットを統合した戦略が欠かせません。
ここで紹介する5つのテクニックを押さえることで、離れた相手にも情報が伝わりやすくなり、対面と遜色ない信頼を構築しやすくなります。
視覚資料の最適化
画面共有の導線設計
バーチャル背景の心理効果
チャットフォロー術
視線誘導ジェスチャ
オンライン特有の課題を補完する形でテクニックを組み合わせれば、通信環境やデバイス差による情報ロスを最小化できます。
視覚資料の最適化
オンラインでは画面サイズや解像度が異なるため、1スライド1メッセージを徹底します。要点は14pt以上、図表は彩度を抑えたコントラスト重視の配色にし、視線の移動距離を短縮します。進行に合わせたアニメーションで情報を小出しにすると、飽和しがちなリモート視聴者の集中力を維持できます。
画面共有の導線設計
共有開始前にデスクトップ通知を切り、不要なタブやアプリを閉じると情報漏えいを防げます。説明箇所にジャンプできるリンクや目次スライドを用意しておくと、話題の脱線にも即応できます。画面切替が多い場合は「共有→停止→再共有」の流れを減らし、視聴者の視点を途切れさせないことが重要です。
バーチャル背景の心理効果
整理された背景画像は余計な情報を排除し、話し手への集中を促します。ブランドロゴや実績グラフを背景の隅に配置すると、無言でも信頼性の訴求が可能です。ただし派手な色や動きのある動画背景は情報過多となるため避けます。自然光風のライティングと合わせると肌色が安定し印象が向上します。
チャットフォロー術
音声で伝えた数値やURLを即座にチャットへ補足すると、聞き逃しリスクを削減できます。相手の発言にも「要点要約+確認質問」をテキストで返すと理解度が高まり、議事録作成の手間も省けます。複数人参加の商談ではメンションを活用して質問先を明示し、討議の流れを整理します。
視線誘導ジェスチャ
ウェブカメラの真横に資料の該当箇所を表示し、指差しやペン型カーソルで示すと視線が自然に集まります。カメラ目線は賛同を求める瞬間に合わせ、共感形成を後押しします。ジェスチャは動作範囲を肩幅内に収めることで画面外ブレを防ぎ、見やすさを保てます。
営業テクニックを習得する方法
成果を再現し続けるには、テクニックを「学習→実践→振り返り」のサイクルで蓄積することが不可欠です。
下記の5つの方法を組み合わせると学習効率が高まり、短期間でも行動変容を実感しやすくなります。
ロールプレイ実践法
日報でPDCAを回す
SNSで情報収集する
営業日誌の活用
動画分析トレーニング
習得フェーズごとに異なる学習手段を選ぶことで、知識定着と現場適用のギャップを縮められます。
ロールプレイ実践法
テクニックを体で覚えるには、ロールプレイが最短経路です。上司や同僚と役割を交替し、毎回一つのテクニックだけに集中すると改善点が明確になります。録画して客観視すると、無意識の口癖や間の取り方も把握でき、次の練習に反映できます。
日報でPDCAを回す
商談結果を「目的→実践→結果→考察」の順で日報に記録し、翌日のアクションに落とし込みます。数字だけでなく感情面や顧客反応も書くと、状況判断の質が高まります。週次で振り返れば改善ペースが早まり、習得効果を客観的に確認できます。
SNSで情報収集する
営業界隈のハッシュタグや音声SNSを活用すると、最新事例やツール情報をリアルタイムで取得できます。信頼度を見極めるために発信者の実績やエビデンスを確認し、取り入れる前に自社業態へ適合させる視点を持つことが大切です。
営業日誌の活用
手書きの営業日誌は思考を整理しやすく、後から検索もしやすい形式で残せます。成功要因と失敗要因を分けて書き、似た商談が来た際に参照できる索引ページを作っておくと再利用性が向上します。継続するコツはフォーマットを固定し、記入時間を10分以内に収めることです。
動画分析トレーニング
自分やトップセールスの商談動画を倍速視聴し、良い点と改善点を箇条書きで抽出します。口癖の回数やアイスブレイク時間など定量化できる指標を設定すると比較が容易です。分析結果を次回ロールプレイに反映し、効果測定を行うと学習ループが完成します。
営業テクニック活用時の注意点

テクニックは万能ではなく、乱用すると短期的成果と引き換えに信頼を損ねる恐れがあります。
次の5つの観点からリスクを把握し、長期的な顧客関係を守りましょう。
過剰テクニックの弊害
顧客志向とのバランス
法令遵守と倫理観
ノルマ依存への対策
顧客満足の定量化
注意点を把握した上でテクニックを使うと、継続受注や紹介につながる健全な営業活動を維持できます。
過剰テクニックの弊害
クロージング手法を多用し過ぎると、顧客は「買わされている」と感じリピートを避けます。
短期的に数字を上げても解約率や値引き要求が増えるため、中長期利益はむしろ低下します。テクニックは目的ではなく手段であることを常に意識する必要があります。
顧客志向とのバランス
顧客の課題解決よりも自社商品の強みを先に語ると、自社都合の押し売りと受け取られます。顧客視点で情報提供し、導入判断を尊重する姿勢を示すと信頼残高が蓄積します。結果として紹介や追加発注の機会が増え、長期売上が安定します。
法令遵守と倫理観
誇大広告や虚偽表示は不当景品類及び表示に関する法律に抵触し、行政指導や罰則の対象となります。業界ガイドラインや社内コンプライアンス規定を定期確認し、最新の法改正に合わせてトークスクリプトを更新することが不可欠です。
ノルマ依存への対策
数字だけに意識が偏ると精神的負荷が高まり、メンタル不調や離職リスクが上昇します。KPIを成約率だけでなく商談満足度や紹介件数など多面的に設定すると、健全な動機付けが働きやすくなります。上司は成功プロセスを評価し、数字に偏らないレビューを行うことが大切です。
顧客満足の定量化
アンケートやNPSを導入し、数値で顧客満足を管理します。フィードバックをトリガーに改善サイクルを回すと、テクニック依存ではなく顧客体験向上が中心の営業活動へ転換できます。数値をチーム共有して学び合う文化を構築すれば、属人化も防げます。
まとめ
営業テクニックは「準備→対話→クロージング→フォロー」の各場面で役割が異なります。ターゲットリサーチから視線誘導ジェスチャーまで多彩な方法を組み合わせることで、顧客の意思決定を自然に後押しできます。
一方で過剰なテクニックは信頼を損ないかねないため、顧客価値を中心に据えた運用が大前提です。
学習と振り返りの習慣を持ち、法令遵守と倫理観を守れば、短期成果と長期関係の両立が可能になります。この記事で紹介した具体策を取り入れ、明日からの商談で成約率向上を体感してください。
貴社が抱える課題に対してより具体的な解決策を知りたい方は、ぜひKEY RAISEまでお問い合わせください。
貴社の現状や目指すゴールに合わせて最適なご提案をいたします。
下記のフォームよりお気軽にご連絡ください。