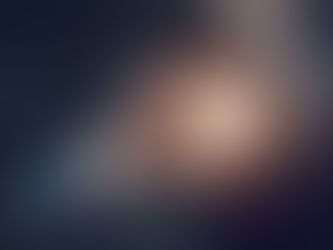営業の属人化の解決策は?起こる原因や解消方法を解説
- プロテア 株式会社
- 6月24日
- 読了時間: 10分
更新日:6 日前
営業担当者に業績が偏り、キーマンが不在になると売上が急減する、そんな“属人化”の壁に悩む企業は少なくありません。
今回の記事では、営業の属人化が起こる仕組みとリスクを整理し、再現性を高めるためのマニュアル整備やSFA・CRMの活用、評価制度の見直しまでを具体策とともに解説していきます。
ぜひ誰が担当しても高い成果が出せる営業チームへ変革するための、参考にしてください。
営業の属人化とは?意味と現状

営業の属人化とは、顧客情報や提案ノウハウが特定の担当者だけに依存し、他のメンバーがすぐに引き継げない状態を指します。ITツールが普及した今も、多くの企業でブラックボックス化が進行中で、急な退職や異動により売上が乱高下しやすいのが実情です。
まずは現状と課題を数字で可視化し、早期対策へつなげましょう。
営業の属人化の定義
営業の属人化とは、商談の進め方や提案書の構成、顧客対応のコツなどが担当者の暗黙知として溜まり、組織で標準化されていない状態を指します。同じ商品を扱っていても担当者ごとに成果がばらつくのは、この暗黙知が共有されず再現性が低いからです。個人に依存したまま業務が続くと、評価や育成が感覚頼りになり、ノウハウ自体も退職とともに消失します。属人化を断ち切るには、経験を形式知化し、チェックリストやテンプレートへ落とし込み、誰でも短期間で成果を再現できる土台を整えることが第一歩です。日々の業務で小さく実践し、改善を積み重ねる姿勢がカギとなります。
現代営業組織における属人化の現状
デジタルツールが一般化した現在でも、営業現場ではExcelや個人PCに顧客リストを保存し、案件管理は担当者の頭の中というケースが散見されます。SFAを導入しても入力ルールが曖昧で、情報が更新されず“空箱化”している企業も少なくありません。その結果、引き継ぎに数週間を要し、年度替わりには売上が一時的に2割近く落ち込むなど、組織全体を揺るがす課題となっています。人材の流動性が高まる中、属人化を放置すれば新人育成も停滞し、営業成果は長期的に伸び悩みます。今こそ抜本的な対策が不可欠となります。迅速に着手しましょう。
営業の属人的な業務の具体例
実際の現場で属人化が進みやすい業務を把握すると、自社のボトルネックが見えてきます。
代表的なケースは次の通りです。
顧客リストや商談履歴を個別のExcelで管理
提案書や見積書を担当者独自のフォーマットで作成
案件進捗をメールや口頭で報告し、履歴が残らない
クレーム対応の手順が担当者ごとに異なる
これらに共通するのは、情報と手順が属人化し、再現性を担保できない点です。まずは上記に該当する項目を棚卸しし、テンプレートやSFAでデータを一元化するだけでも、属人化リスクは大きく軽減します。
なぜ属人化が問題視されるのか
属人化が放置されると、いざという時に売上が止まるだけでなく、組織学習の速度が著しく低下します。ノウハウが形式知化されず、試行錯誤が各自バラバラに繰り返されるため、同じ失敗が横行し、育成コストも膨らみます。
さらに、担当者に負荷が集中しバーンアウトや離職が発生すると、顧客との関係性まで失われる二次被害が発生します。結果として経営層は人員補充と顧客回復に追われ、戦略立案に集中できません。
営業属人化のリスクとデメリット
属人化を放置すると、引継ぎ停滞や顧客離反など短期的な損失だけでなく、育成停滞・離職増加といった長期的ダメージへ連鎖します。
ここでは代表的な4つのリスクを整理し、なぜ早期対策が欠かせないのかを具体的に解説していきます。
業務停滞と機会損失
担当者が急に不在になると、顧客対応が数日止まり商談が失注しやすくなります。中でも大型案件は交渉のタイミングを逃すと再獲得が困難で、年間売上の1〜2割が一気に失われるケースもあります。属人化した状態では、顧客履歴・提案内容が共有されておらず、後任が全体像を把握するのに時間がかかる点が最大の問題です。定期的な情報入力ルールを設け、誰でも最新状況を確認できる仕組みが欠かせません。
生産性・再現性の低下
同じ商品を扱っていても、担当者ごとに提案資料の構成や商談プロセスが異なると、社内でベストプラクティスが共有されず、生産性が頭打ちになります。属人化の顕著な組織では、成約率が人によって10〜20ポイント差が開くのが一般的です。業務フロー・資料フォーマットを統一し、成功事例をテンプレート化すれば、経験年数に左右されず成果を再現できる体制が整います。
育成・評価の歪み
ノウハウが暗黙知のままだと、若手は試行錯誤に追われ短期間で成果を出せず、自己効力感が下がります。また、評価指標が売上のみだと情報共有に消極的になり、学習文化が根付かないまま優秀層の離職を招きやすくなります。プロセス指標やチーム貢献度を評価に組み込み、ナレッジ共有を促す制度設計が不可欠です。
ストレスと離職リスク増大
顧客管理や案件進行を1人で抱え込む環境は精神的プレッシャーが大きく、残業や休日対応が常態化しがちです。結果としてバーンアウトや離職が発生し、人員補充と顧客回復に時間とコストが再投入される悪循環に陥ります。クロス担当制や定例ミーティングで負荷を平準化し、メンタルケアの体制も並行して強化しましょう。
営業属人化が起きる主な原因

「気づけば担当者頼み」
この状態を招く背景には、仕組み不在・文化の偏りなど複数の要因が絡み合っています。
ここでは重複を避けつつ、属人化を引き起こす4つの根本原因を整理します。
標準化されていない業務フロー
商談の開始からクロージングまでの手順が文書化されていないと、担当者ごとにアプローチがばらつきます。新人は「見て覚える」方式に頼り、習熟に時間がかかるうえ、成功事例が社内に蓄積されません。結果として、再現性の低さが長期的な売上停滞を招きます。
情報共有インフラの不足
SFAやCRMを導入していても、入力ルールが曖昧であれば“空箱”化しやすく、肝心の顧客履歴が個人PCに眠ったままになります。共有ストレージが部署ごとに分散している企業も多く、検索性の低さが「探すより自分で作る」文化を助長。情報のサイロ化が属人化をさらに深刻化させます。
成果偏重の評価制度
売上全振りのKPIは短期成果を出す分には有効ですが、ノウハウ共有やチーム貢献が評価されないため、情報囲い込みが常態化します。ベテランが自分の方法論を公開しないまま異動・退職すると、ノウハウ損失が発生し、若手の育成スピードも落ち込みます。
ナレッジの形式知化不足
「マニュアルは作ったけど更新されていない」「誰も読んでいない」といったケースでは、実質的に口伝中心のOJTが続きます。属人的な経験談が暗黙知のまま循環し、トラブルやクレーム対応も個人裁量に依存。結果、業務品質のばらつきが解消できません。
営業属人化を解消する5つの方法
原因を踏まえ、実効性の高い打ち手を5つに絞りました。どの施策も単独で効果がありますが、組み合わせると相乗効果が生まれ、脱属人化が加速します。
マニュアル・チェックリスト整備
業務フローを図解し、要所ごとにチェック項目を設置。更新責任者と頻度を決め、現場の声を吸い上げながら改訂を続けることで「読まれるマニュアル」へ進化します。作成ツールはPowerPointでもNotionでも構いませんが、検索性と履歴管理を考慮してクラウド上で一元管理しましょう。
SFA・CRMの徹底活用
導入で満足せず、入力フォーマットを厳格化し「空欄不可」の必須項目を設定。ダッシュボードで進捗を可視化し、週次ミーティングで未入力案件を確認すると、現場の入力率が劇的に改善します。API連携でメールやカレンダーから自動取得すれば、入力負荷も抑えられます。
クロス担当制の導入
重要顧客や大型案件は最低2名で担当し、商談準備から報告までをペアで行います。協働を評価に反映させることで、情報共有が当たり前の文化に転換。担当者が不在になっても、相方がスムーズにフォローでき、顧客体験を損なわずに済みます。
段階別育成プログラム
新人・中堅・ベテランの3層に分け、必要スキルを定義。ロールプレイや録画商談のフィードバックを通じて暗黙知を形式知化し、学習コンテンツとしてSFA上で再利用します。「教える側」も評価対象にすることで、ノウハウの囲い込みを防ぎます。
プロセス+チーム貢献型評価へ刷新
売上と同じ比重で、SFA入力率・テンプレ更新回数・勉強会の登壇数などを評価指標に追加。個人の成果だけでなく組織学習への寄与度が認められると、情報共有がインセンティブ化され、属人化の再発を防止できます。
属人化解消の成功事例
施策を実行した企業の成果を3例紹介します。自社の規模や課題と照らし合わせ、導入イメージを具体化してください。
マニュアル統一で商談失注率3割改善
製造業A社は、6部門でバラバラだった提案書フォーマットを1か月で統一。チェックリストで必須項目を明示した結果、顧客質問への即答率が向上し、失注率が28%改善しました。更新は各部門の代表が持ち回りで担当し、常に現場目線の内容を維持しています。
SFA定着で引継ぎ工数50%削減
IT企業B社は、SFA入力を「毎営業日終了後15分」とルール化。未入力案件は翌朝自動リマインドを送信し、月末には入力率98%を達成。離職者が出ても平均引継ぎ期間が2週間から7日に短縮され、顧客への対応遅れが大幅に減少しました。
共有文化醸成で離職率半減
ベンチャーC社は、週1回の「ノウハウ共有ランチ」を導入。登壇した社員には評価ポイントと小額のピアボーナスを付与したところ、1年後の営業部離職率が18%から9%へ半減。属人化が解消されただけでなく、チームワークが強化されました。
導入時の注意点
マニュアル更新やSFA入力は「やらされ感」が強いと形骸化しがちです。経営層が先頭に立ち、目的とメリットを共有し続けることが成功の鍵。施策を段階的に展開し、早期に「成果が見える小勝ち」を演出すると現場が前向きになります。
チェックリストとテンプレート活用術

脱属人化の第一歩は「現状把握」と「ツール整備」です。
以下のチェックリストとテンプレート構成を参考に、自社用にカスタマイズしてください。
属人化チェック5項目
SFA入力率が90%未満
提案書フォーマットが3種類以上存在
顧客への返信スピードが担当者で大きく異なる
引継ぎに2週間以上かかる
月次勉強会の開催頻度が0回または不定期
共有マニュアルの基本構成
業務フロー図(全体像+担当分担)
提案書・見積書テンプレート
営業チェックリスト
トラブル対応フロー&FAQ
更新履歴と担当者リスト
引継ぎ時の3ポイント
顧客要望・購入決定プロセスをSFAメモで時系列管理
次回アクションと期限をダッシュボード表示
引継ぎ完了後、クロス担当者がフォローコールを実施
今すぐ始められる小さなアクション
今日からSFAメモ欄に「次回約束日」を必ず入力
週1回15分のノウハウ共有をカレンダー固定
既存テンプレートを1ファイルに集約しSlackで告知
まとめ
営業属人化の最大の敵は「明日やろう」という先延ばしです。まずはチェック項目を1つ実行し、小さな成功体験を積み上げましょう。
業務フローの文書化、SFA入力ルール、クロス担当制、育成プログラム、評価制度など、これらを段階的に組み合わせれば、誰が担当しても成果が再現できる強い営業組織へ必ず変革できます。
「今日」行動を起こすことが、明日以降の安定した売上と働きやすい職場を作るでしょう。
貴社が抱える課題に対してより具体的な解決策を知りたい方は、ぜひKEY RAISEまでお問い合わせください。
貴社の現状や目指すゴールに合わせて最適なご提案をいたします。
下記のフォームよりお気軽にご連絡ください。